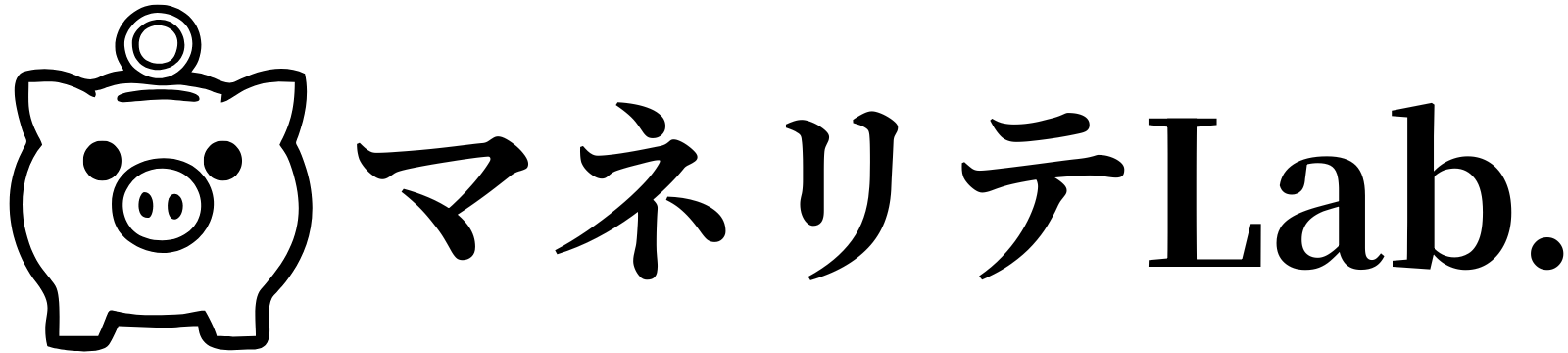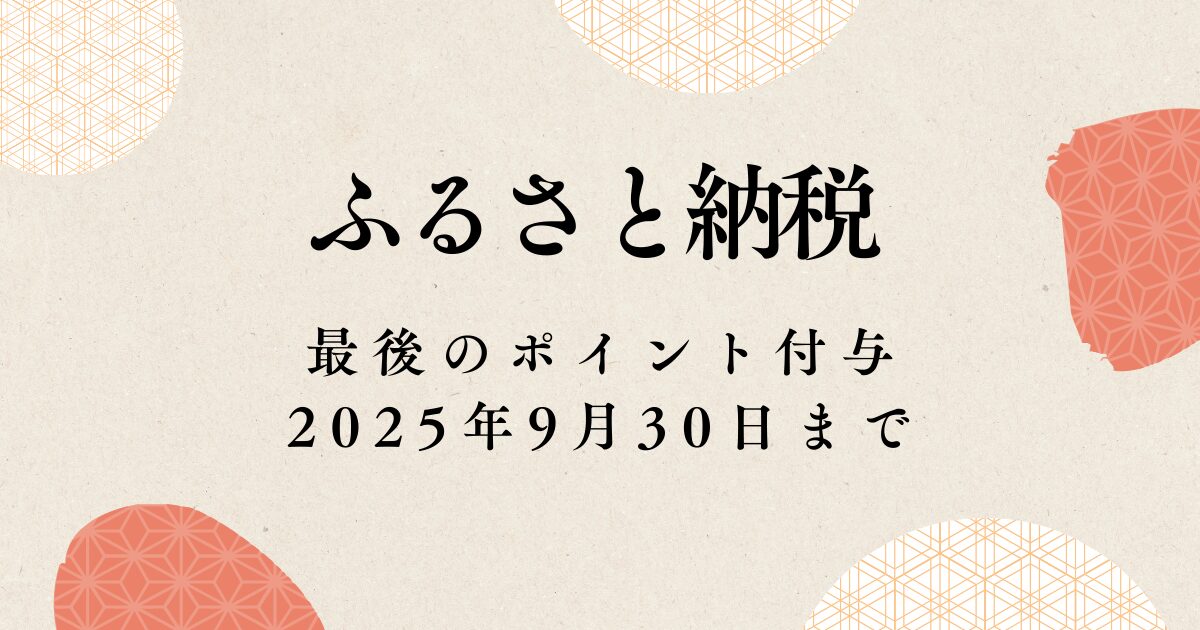2025年も半分が過ぎました。
夏の賞与も終わり、冬の賞与の査定期間に入っていますね。
一生懸命頑張っているのに、会社や職場で評価されずに辞めたくなる…そういった経験がある人も居るのではないでしょうか。
私は地方の中小企業ですが、20人の部下をまとめる管理職をしていた経験があります。
平社員の部下や、管理職の部下の人事評価も行っていました。
そんな経験から、会社や職場で評価されない時に確認したい3つのポイントについてFPが詳しく解説します。
賞与や昇給に向けて評価をレベルアップしましょう。
・個人の仕事の能力の評価について
・会社や職場で評価されない時に確認したい3つのポイント

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
- 資産形成コンサルタント
- 投資診断士
個人の仕事の能力の評価について
人それぞれ色々な人が居ます。
能力が高く何でも卒なくこなす人も居れば、真面目にやっているけど能力が低く人並以下の成果しか出せない人など様々です。
当然、前者の方が評価は高くなるのかもしれませんが、後者に仕事をしてもらって成果を出すのが管理職の仕事でもあります。
能力が低い人にも適材適所があったり向き不向きがあったり、その個性を扱っていくのも管理職の仕事なんですね。
その点では、結果や成果は管理職の腕にかかっているといっても過言ではなく、両者とも仕事を任せている部下であり同じ観点です。
しかし、だからといってそれでいいという話ではなく、能力が低い人でも3つのポイントさえ押さえていれば欠点をカバーでき、技術面ではなく人間面で評価を上げることができます。
逆に仕事が出来て技術面が高くても、3つのポイントが出来ておらず人間面で評価が低いと私は満点を与えませんでした。
そんな重要な3つのポイントについてお話します。
会社や職場で評価されない時に確認したい3つのポイント
- ホウレンソウは確実にする
- 勝手な判断をしない
- 自己評価と比較
この3つ簡単そうで出来てない人が非常に多いんです。
細かく説明していきますので、本当に該当していないかチェックしてみて下さい。
該当してなければ、あなたは既にしごでき社員です。
ホウレンソウは確実にする

報告・連絡・相談ですね。
これは部下だけがやるのもではなく、上司もやるべきことでもあります。
リアルタイムで報告・連絡・相談できないものに関しては仕方がありませんが、事後報告では困る内容であることも多くリアルタイムで報告・連絡・相談することによってお互いの仕事の精度が上がります。
・後で出会ったときに言えばいいや
・聞かれたら言おう
・言わなくても見たら分かるだろう
このような考えをしていませんか?
後で出会ったときに言えばいいや
仕事中は様々な変化に対応しながら過ごしていますので、後で言おうと思っていても忘れてしまったりすることも普通にあります。
あとで言うつもりが上司が会議でそのまま出会うことなく終業なんてこともあるでしょう。
それが積み重なり、事後報告ばかりになると信頼を失うきっかけにもなります。
聞かれたら言おう
先手必勝です。
頼んだあれどうなった?と聞かれる前に終わったなら一言、自分から報告しましょう。
仮に終わっていなくても、いつ頃になりそうですけど大丈夫ですか?と一言いいましょう。
その一言が部下の方からあるだけで、仕事に対して責任を持って対応してくれている姿勢を感じ取ることができます。
言わなくても見たら分かるだろう
実際、仕事の進捗を見れば言われなくても分かることもあるかもしれませんが、報告・連絡・相談もコミュニケーションの1つです。
 たまご
たまごホウレンソウができると責任感の評価もあがるよ!
勝手な判断をしない

これが最大の難しいところなんです。
何が難しいかというと、本人は勝手な判断どころか最善の判断をしているところなんですね。
仕事上で選択や状況判断の局面になった時、自分の経験・知識・様々な状況から自分で判断できる内容と認識し判断します。
この判断力は必要なものであり、常に1つ1つ確認していたらお互い仕事になりませんよね。
しかし最善の判断をしたはずなのに実は勝手な判断を知らないうちにしており、その判断によってミスが生じてしまうのです。
ミスが多い人はこのタイプが結構多いです。
最善の判断が、なぜ勝手な判断に変わってしまうのか見てみましょう。
例えば、過去にAという事象が起きBという対応をしたとしましょう。
今Aという事象が起き、仕事の担当者のCさんは、Aという事象が起きた時の過去の経験や知識から同じようにBの対応を取りました。
これ、勝手な判断しちゃってるんですけど何が問題なのか分かりますかね。
も少し分かりやすくすると
過去にAという事象が起きBという対応を取りました。
今Aという事象に凄く似ているDという事象が起き、仕事の担当者のCさんは、考えた結果Aという事象が起きた時の過去の経験や知識から同じような対応で良いと判断しBの対応を取りました。
これならどうでしょうか?
後者は、過去の経験や知識から類似の事象だからと憶測で判断をしていますよね。
一方、前者の何が問題かというとAという事象が起きた原因が、Bという対応をとった時と全く同じならその対応でいいんです。
しかし、Aという事象が起きた原因が過去と違った場合は、必ずしも前回と同じBの対応で良いとは限りません。
人間は成功体験によって成長していきます。
何回か同じ様な判断を下した経験があり、たまたま毎回Bの対応で良かった場合はAが起きた原因について考えることがないんですよね。
Aが起きたらB、これだけが必要な情報となってしまいます。
そして、いざその時が来た時に失敗するのです。
これについての対応策はいたって簡単です。
今Aという事象が起きたのですが、いつものようにBの対応で大丈夫ですか?
今Aという事象に凄く似ているDという事象が起きました。
Aという事象が起きた時のBの対応で大丈夫ですか?
自分の考えた判断で良いかを上司に確認すればよいだけです。
確認し、上司を巻き込み指示を仰ぐことであなたの責任ではなくなります。
上司がろくに確認もせず適当に返事した結果ミスが起きても、上司が考えた結果GOを出してミスが起きたとしてもあなたの失敗ではなく上司の判断ミスです。
上司はその為に居ますので上手く利用しましょう。
私はそういつも部下に言ってました。
この勝手な判断というのは、自分で判断してはいけないということではなく、確認するという選択肢があるにも関わらず確認せずに判断することを指すことを覚えておきましょう。
不在で確認することができず、自己判断で進めるしかなかった場合は仕方がありません。
自己評価と比較

自己評価は自己評価なので、自分の思うように自分を評価してもらって構いません。
しかし、実際の評価と自己評価を比較し落胆したり苛立ったり開き直ったりするのはよくありません。
私はこんなにも頑張っているのに…、それはあくまで自己評価であり誰が見ても本当にそうなのでしょうか?
本当にそうなのであれば評価として返ってきていてもおかしくありません。
自分が頑張っているかどうかは自分だけが決めることではなく、周囲や上司も認めて初めて頑張っているとなることを忘れてはなりません。
自己評価と実際の評価に差が生じた場合、自分に何が足りていないのかを見つめ直すことが大事です。
まとめ
この記事では、会社や職場で評価されない時に確認したい3つのポイントについて説明してきました。
- リアルタイムでホウレンソウを行う
- 勝手な判断はせず上司に確認を取る
- 自己評価は自由だが最終的な評価は周囲や上司が評価
この3つのポイントを押さえるだけで、仕事上のミスが減り結果、評価のアップに繋がると思います。
確認やホウレンソウでコミュニケーションを取り合うことで、お互いの信頼度も上がりますので是非意識してみて下さい。