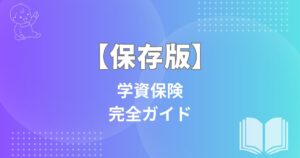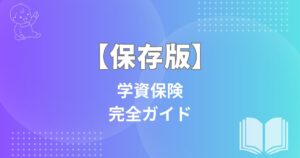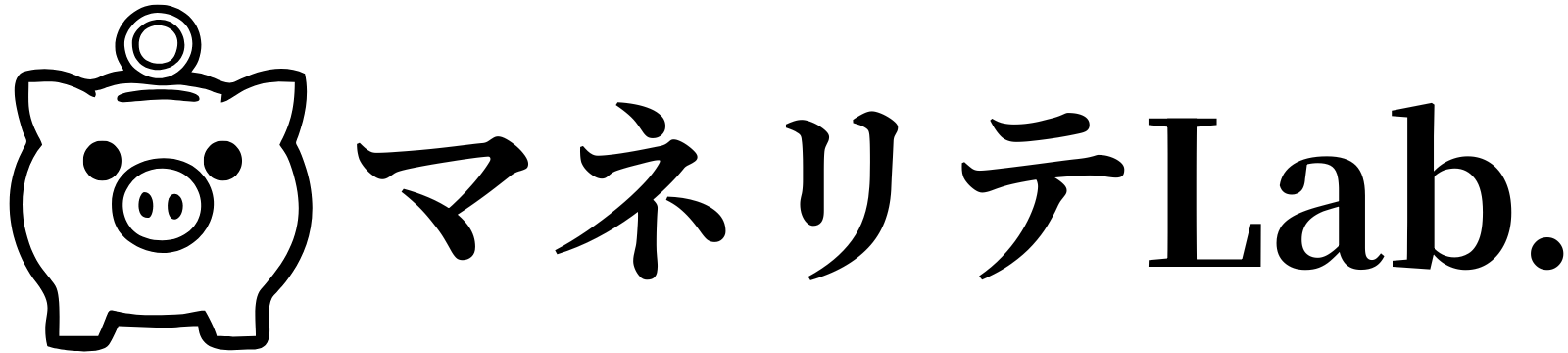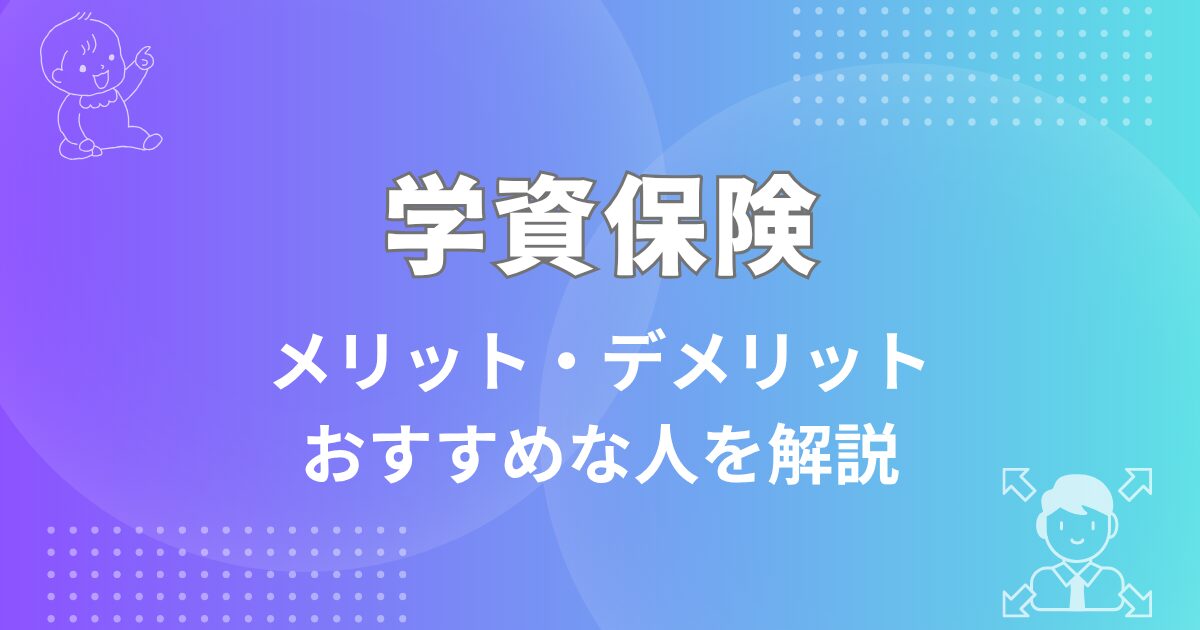教育資金捻出方法の1つである学資保険。
学資保険って実際どうなの?と思われている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、学資保険のメリット・デメリット、保険特性からおすすめな人や生命保険料控除についてFPが詳しく解説します。
・学資保険のメリット
・生命保険料控除の節税シミュレーション
・学資保険のデメリット
・学資保険がおすすめな人

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
- 資産形成コンサルタント
- 投資診断士
学資保険とは
学資保険について知りたい人は、こちらの記事で詳しく解説しています。
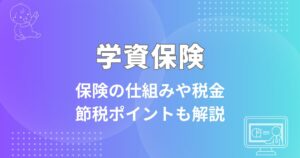
学資保険のメリット
- 契約者に万が一があった場合保険料の払込が免除される
- 生命保険料控除の対象
契約者に万が一があった場合保険料の払込が免除される
一般的に学資保険は、契約者が死亡または保険会社所定の高度障害状態となった場合、以後の保険料の払込みが免除されます。
払込みが免除となった場合でも、満期保険金の受取時期に満期保険金が支払われます。
 たまご
たまご団体信用生命保険みたいな安心感があるね!
生命保険料控除の対象
学資保険は生命保険料控除の対象となり、年末調整または確定申告することで所得控除できます。
| 年間払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超~4万円以下 | 支払金額×1/2 +1万円 |
| 4万円超~8万円以下 | 支払金額×1/4 +2万円 |
| 8万円超 | 4万円 |
よくある控除は、所得税で引ききれなかった分を住民税から、といったものが多いですが、生命保険料控除は所得税・住民税どちらからも控除されます。
生命保険料控除による節税効果も加味すると実質返戻率も上がります。
おおよそ、どのくらいの節税効果があるのか見てみましょう。
・年収400万円と仮定
・18年間の保険料払込と仮定
・満期保険金300万と仮定
・返戻率105%と仮定
・所得税・住民税10%で算出
| 節税シミュレーション | |
|---|---|
| 毎月の保険料 | 13,228円 |
| 年間保険料 | 158,736円 |
| 年間節税額 | 6,800円 |
| 総節税額 | 122,400円 |
| 実質返戻率 | 109.7% |



約9か月分の保険料がタダになったようなもんだね!
学資保険のデメリット
- 途中解約すると元本割れの可能性がある
- インフレリスクがある
途中解約すると元本割れの可能性がある
途中解約した場合、それまでに払込んだ保険料総額に応じて解約返戻金が支払われますが、払込保険料の総額を下回る可能性があります。
返戻率は満期まで加入前提で割り出されており、運用期間が短い、支払保険料の一部は経費等に使用、などの理由によって途中解約すると損する可能性が高くなっています。
インフレリスクがある
学資保険は、加入から満期を迎えるまでに18年など長い期間となります。
この間も、少なからずインフレの影響は受けます。
現在価値で教育費を算出し、満期保険金の金額を決定すると実際に必要な教育資金をまかなえない可能性があります。
対策としては、変動率を考慮しインフレを見込んだ教育費の金額設定にすることが重要です。
学資保険がおすすめな人
- 自分に万が一のことがあった場合も子供に資金を残したい
- 節税したい
- 貯蓄が苦手
自分に万が一のことがあった場合も子供に資金を残したい
貯蓄など他の手段であれば万が一のことがあった場合そこでストップしますが、学資保険であれば満期保険金の受取は約束されています。
子供の為にもその様な保障が欲しい場合は、学資保険がおすすめと言えます。
節税したい
生命保険料控除を保険料を払い込んでいる間、毎年受けることができます。
節税しながら教育資金の捻出をしたい方もおすすめと言えます。
貯蓄が苦手
保険料は口座を通して引き落とされますので、強制的に積立ていくことができます。
また、自由に引き出すことはできませんので他の用途に使ってしまう心配がなく、貯蓄が苦手な人でも確実に教育資金を捻出できるのでおすすめです。



学資保険を検討する場合は子育てママに特化した無料保険相談サイト【ベビープラネット】がおすすめだよ!
まとめ
この記事では、学資保険のメリット・デメリット、保険特性からおすすめな人や生命保険料控除について説明してきました。
- 契約者に万が一があった場合保険料の払込が免除される
- 生命保険料控除の対象
- 貯蓄が苦手な人でも教育費を捻出できる
- 途中解約すると元本割れの可能性がある
- インフレリスクがある
- 自分に万が一のことがあっても子供に資金を残したい人、節税したい人、貯蓄が苦手な人におすすめ
学資保険は途中解約さえせず継続できれば、万が一の保障や所得控除などお得に教育資金を捻出できる手段です。
保険の内容をよく理解し、教育資金捻出の手段の1つとして考えてみてはどうでしょうか。