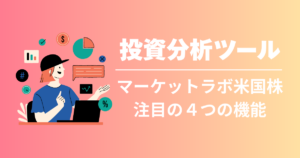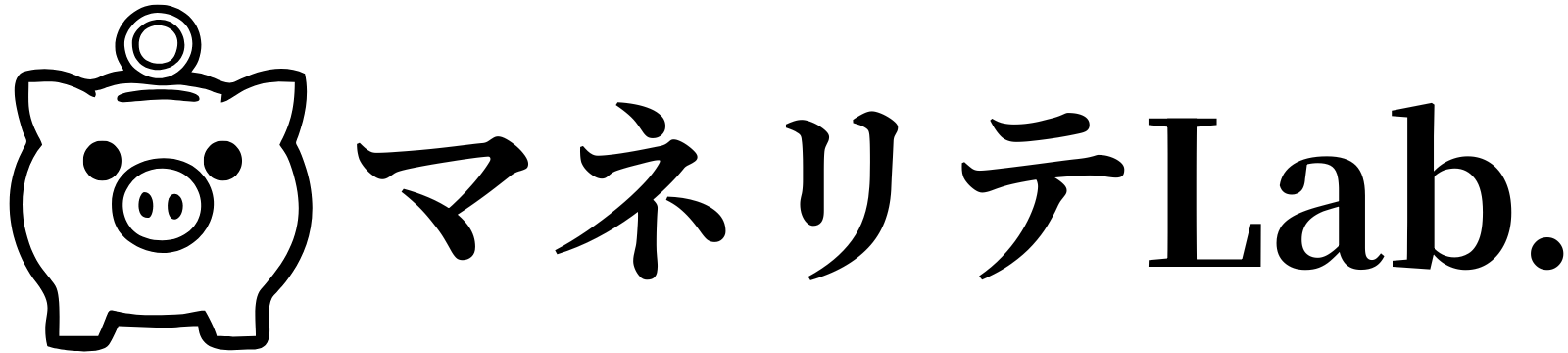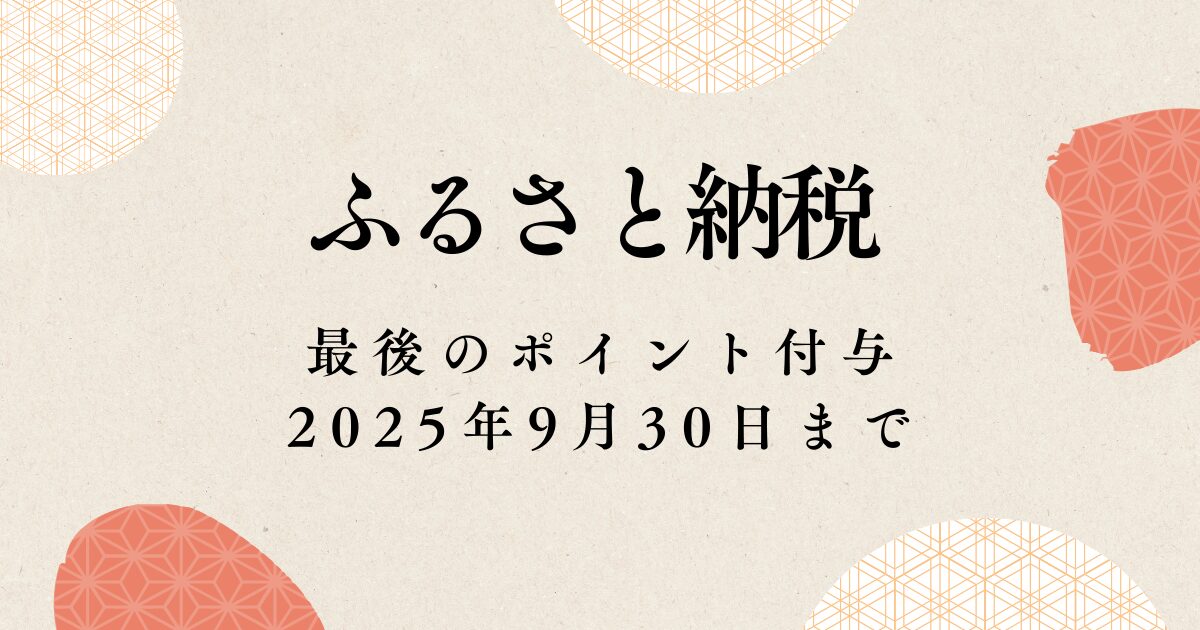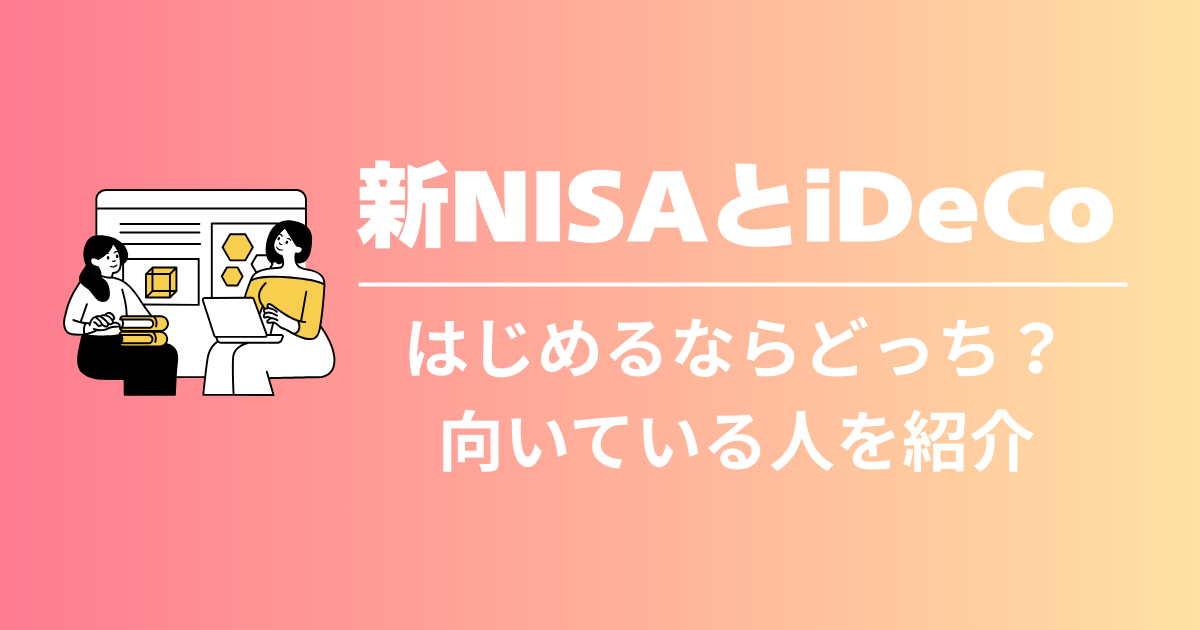これから投資を始めようと考えている人の中には、新NISAとiDeCoどちらをはじめた方がいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。
2つとも非課税で運用でき、投資の手段としては優れた制度です。
制度の性質を理解することで、自分にどちらが合っているか知ることができます。
この記事では、新NISAとiDeCoどちらが良いかについてFPが詳しく解説します。
・新NISAとiDeCoどっちがいいか
・新NISAとiDeCoの比較
・新NISAが向いている人
・iDeCoが向いている人

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
- 資産形成コンサルタント
- 投資診断士
NISAとiDeCoとは
新NISA制度やiDeCoについて知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

新NISAとiDeCoはじめるならどっち
結論は新NISAとiDeCo可能なら両方した方が、より税制面で恩恵を得ることができます。
しかし、どちらか一方から始めるなら制度の性質と流動性の観点から新NISAをお勧めします。
新NISAとiDeCoの比較
新NISAとiDeCoの概要をまとめました。
| 新NISA | iDeCo | |
|---|---|---|
| 投資対象 | 18歳以上 | 20歳以上 |
| 投資可能期間 | 無期限 | 65歳まで |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 60歳~75歳の間 |
| 年間投資枠 | 360万円 | 区分による |
| 非課税限度枠 | 1,800万円 | 区分と期間による |
| 投資対象 | 上場株式・投資信託 | 投資信託・保険商品・預貯金等 |
| 投資方法 | つみたて/自由 | つみたて |
| 運用益の受取 | 自由 | 加入期間10年以上を 満たした60歳以降 |
| 運用コスト | なし | 加入時2,829円 運用管理手数料171円/月 口座管理手数料0円~500円程度/月 |
| 税の優遇処置 | 運用益が非課税 | 運用益が非課税 掛金が全額所得控除 受取時に各控除適用 |
運用益の受取、手数料の観点から新NISAの方が気軽に始めることができます。
特に投資初心者に多い不安要素である
- 毎月継続できるか分からない…
- 途中でお金が必要になるかもしれない…
こんな不安に対してもいつでも換金できますし、辞めたり放置しても運用コストはかかりません。
この点が新NISAをおすすめする最大の理由です。
一方、iDeCoはこれから投資を始めようとする人にとって、流動性や運用コストの点で気軽に始めにくい感が否めません。
新NISAが向いている人
- これから投資をはじめる人
- 投資経験者
これから投資をはじめる人
これから投資を始めようとする人にとって、いつでも辞めたり休んだりで換金できる点が気軽に始めやすく向いていると言えます。
投資経験者
投資経験者でも幅広い商品を選択し、自分の目的に合った投資手法が取れますので不足ないと言えます。
まとめ
新NISAは投資によって資産形成したい人に向いていると言えます。
 たまご
たまごNISA口座を開設するならNISA応援プログラムで2000ポイント貰える松井証券がおすすめだよ!
iDeCoが向いている人
- 節税の恩恵を最大に受けたい人
- 公的年金以外で年金を捻出したい人
- 新NISAを満額運用済の人
節税の恩恵を最大に受けたい
運用益の非課税に加え、掛金や受取にも控除を受けることができますので節税の恩恵を最大に受けたい人に向いていると言えます。
特に、自営業の方などは掛金の金額が高額なので節税効果も高くなります。
公的年金以外で年金を捻出したい人
iDeCoはリスクの少ない定期預金や保険商品など安全な商品も選択することができ、堅実に年金を捻出したい人に向いていると言えます。
特に、自営業などの方は退職金制度がなかったり基礎年金しかありませんから自分で老後資金を補強していく必要があります。
新NISAを満額運用済の人
新NISAを既に満額運用済でなお、余剰資金がある人は特定口座の運用と一緒にiDeCoを検討してみてもいいかもしれません。
まとめ
iDeCoはあくまで投資は手段の1つであり、節税や年金の捻出を目的にしている人に向いていると言えます。
 たまご
たまごiDeCoを始めるなら運営管理機関手数料が0円のマネックス証券 iDeCoがおすすめだよ!
まとめ
この記事では、新NISAとiDeCoどちらが良いかについて説明してきました。
- 始めるなら新NISA
- 新NISAは投資で資産形成したい人におすすめ
- iDeCoは節税・年金捻出・新NISAが満額な人におすすめ
制度の違いにより、どちらが自分に合っているのか明確になったと思います。
自分のライフプランに合った制度を利用し、資産形成を行っていきましょう。